広島国際映画祭 舞台挨拶レポート
INFORMATION |
広島国際映画祭のオープニング上映を実施。上映終了後に黒崎博監督登壇の舞台挨拶を、そして別会場でワークショップを行いました。そのトーク内容を一部レポートいたします。
11月19日(金)広島県NTTクレドホールにて
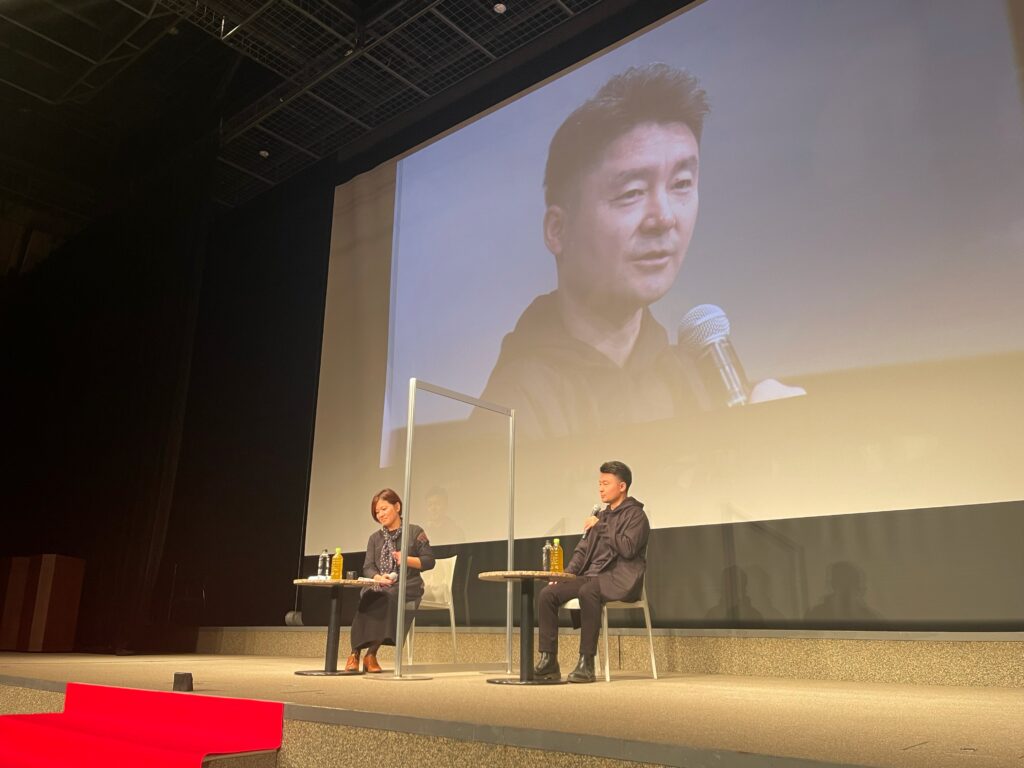
本作で描かれる広島について
「事実を元にした映画なので、現実にこういうことがあったという重さを忘れないように創ろうという想いが強く、また出演者・スタッフの熱量も並々ならぬものがありました。とはいえフィクションの中で、どうやって広島が被爆した現実を伝えたら良いんだろうと。今の技術だったら全てCGで映像を作ることもできたわけですが、考えた末に(出たアイデアが)、広島の平和記念資料館に入ると真っ先に目に飛び込んでくる廃墟となった広島の写真でした。それをなんとかお借りして、現実の力をちょっとでもお借りして表現したいと思って、記念資料館と折衝を重ね、写真の権利者とも折衝を重ねて使わせていただくに至りました。少しでも現実とフィクションの融合ができたら、と思って作ったシーンです。フィクションは「嘘」な訳ですが、嘘を伝えたい訳じゃない。本当のことを伝えるためにフィクションで描くわけですから」

長期間かかった製作期間について
「この尖ったテーマで映画を作るのは本当に大変でした。10数年かかってしまった。しかしその10数年の間に日本の中でも色々なことが起きて、科学の力を使って人間が生きていくということはどういうことか、というのを見つめ直す動きが少し生まれてきた様な気がします。無理だと言われ続けてきた映画製作が、「やろうよ」と言ってくれる人がちょっとずつ増えてきた。必要な年月だったのかもしれません」
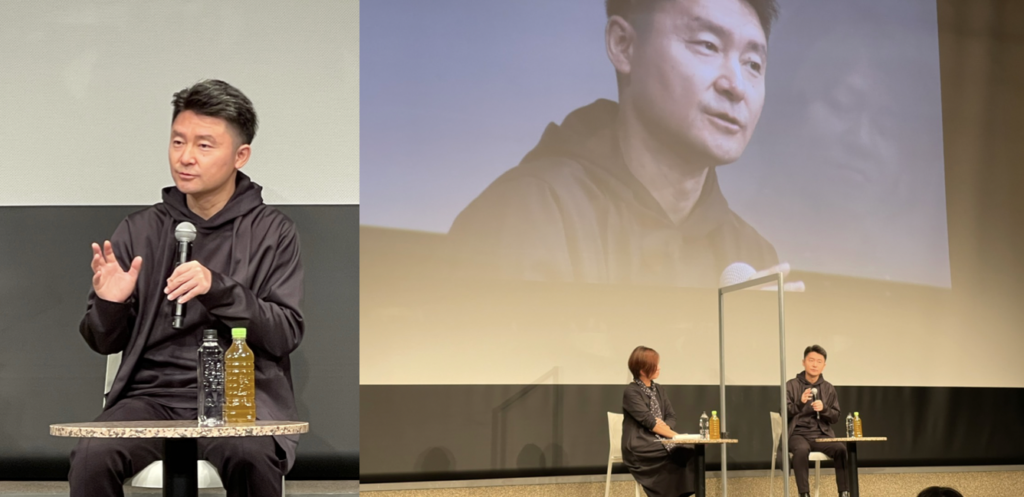
キャスティングについて。まずは石村修役を演じた柳楽優弥さんについて
「当時の研究員たちは、戦争のために科学をしているんじゃない。未知の何かを解き明かすために科学をやっていた。ものすごく真剣に、かつ純粋に研究していた。この物語の主人公はある種の無邪気さがないといけない。まっすぐなだけに罪深い。主人公は優しい奴なのですが、どこか心の中で、科学で何か見つけられるんだったら、何かが犠牲になってもしょうがないって思っている。それくらい純粋なんです。時としてそれは、常人の域を超えていく。そういったある種の狂気を表現するには、柳楽優弥しかいないと思っていました。アカデミックな狂気、とでも言うんでしょうか。眼の底をのぞき込むと静かに炎が燃えているような。そんな芝居をできるのが柳楽くんじゃないでしょうか。いわゆる分かりやすいヒーローとは対極にいるキャラクターですが、観る人を突き放すのではなく、「分かるよ、その気持ち」と最後には言ってもらえるような人物にしたい。柳楽くんとはたくさん話し、悩みながら一緒に作り上げていきました」
朝倉世津を演じた有村架純さんについては
「彼女が、“人としての強い芯”を持っているかというのは、少しは感じて知っているつもりなので脚本を書いている時から有村さんにやってもらいたいと思っていました。有村さんが演じた世津や田中裕子さんが演じた母・フミ。この2人の女性は戦時下にあっても何も見失うことなく「自分の中で何が大事か」を忘れないように生きていた二人だと思う。だから、いざという時に人としての強さを発揮できるのはお母さんであり世津だったと思います。有村さんは自分に対して厳しい考えを持っていてストイックな人なので、この映画のメッセージの中で一番大切なものを託せたのかなと思います」
石村裕之を演じた三浦春馬さんについて
「ご覧ただいた通り、彼は全力でこの映画に望んでくれた。それがそのままスクリーンに残っていると。そこは自負しています。
アツい人なんですよ。脚本読んでくれた時から「絶対やりましょう」と。「これは世に出さなきゃいけない。全力を傾けてやります」、と言ってくれました。その言葉がこのプロジェクトが大きく動くキッカケにもなりました。
海でパニックになるシーンがあります。そのシーンも並々ならぬ集中力で撮影したのですが、その後で兄と家で酒を酌み交わす、一升瓶で酒をつぐシーンがあります。海でのシーンは「この人壊れてしまう」というくらい痛々しい人間の弱さをさらけ出していた彼が、パッとシーンが変わって酒を注ぐシーンになると、本当に朗らかな表情を見せる。注いでる腕の筋肉は惚れ惚れするし、それら全てが重なって、何かふっきれた、覚悟を決めた人間をそこに感じて、現場でハッとしたのを覚えています。全身を使って生き様を表現する人なんですね。」
アメリカでの公開も直前に控え、日米合作の取り組みについて
「原爆開発をテーマにした本作だからこそ、日本だけで作りたくなかった。日米の戦争の作品だからこそあえてアメリカのチームと組んでやりたかったのです。日本で撮影をし、アメリカで仕上げの作業を行いました。カナダまで行って声を録ったり。国境を超えて仕事をするというのをこの作品だからこそやっていきたかったし、そのコラボレーションはこの映画に力を与えてくれました」

1時間弱のロング舞台挨拶を終え、会場を変えて、ワークショップへ。
ワークショップでは、資料を見せながらさまざまなお話が飛び出ました。なかでも、黒崎博監督が本作を撮るきっかけになった京都大学の学生の日記に、知られざるキャラクターたちのもとになるエピソード、取材のエピソードも伺いました。
本作の元になった日記にはどういうことが書かれていたのか?
「そもそもは図書館で日記を見つけたことが作品のスタートです。京都帝国大学の原子物理学をやっている学生が書いたもの。なぜ広島の資料の中に京都の学生の日記があるのか、不思議でした。読み進めていくと8月6日の原爆投下前後のことが中心に載っていた。
この日記は清水栄さん、研究室の中では助手の日記です。映画の中では尾上寛之さんが演じた清田薫の立ち位置のイメージ。若手リーダーみたいな立場ですね。
『風呂を借りに、研究室のマツイ、イシダケ、モリの三人が来た。敵の本土上陸は今年中には無いだろう。沖縄でさえあの大出血を許容されたアメリカがそうやすやすと本土にやってくるわけはない』といったことから書かれていました。
『7月8日。夕方5時。美しい爽快な日曜日であった。連日の寝不足で午前も午後も寝た。久しぶりで家の風呂を焚いて入る。真っ青な青空に浮かぶ白い雲は、戦争の激しい現実と離れて、人々の心を美しい自然へと向ける。比叡山をはじめ山々はくっきりと浮かび上がっている』これを読んで、絶対に比叡山は撮ろうとおもいました。
『4日の夕方、突然弟のタモツが帰宅した。驚きかつ喜ぶこと甚だしい。彼の部隊は5月に鹿児島県川内市に移動した。彼は胸を患っていて入院中なので部隊が移動したが後に残されたのだ。特に二ヶ月間に限って帰郷を許されたとのこと。8月26日までに鹿児島第一線に行けば良いとのことである』
弟が帰ってきたんですね。
こういうモチーフの一つ一つが、自分の中で醸成されてストーリーに繋がっていきました。実際に弟が戦線から帰ってきたわけですよね。期限付きで。でも8月26日までには部隊に戻るということになっていた。幸いにもこの方の場合は戻る前に戦争は終わったわけです。弟は死なずに済んだのだろうと思います。映画ではその前に戦線に戻っていくという設定にさせてもらいました。
科学者の日記と言いながら、科学の記述がまだ出てきてないですが、ちょっとは出てくるんですよ。こういった生活が書かれいていることで、遥か遠くにいる“原子物理学者”がとても近く感じ、自分たちと同じだなと思ったわけです。ですのでこの物語をやってみたいと思いました。
これまでの小説、映画、ドラマで戦争のことや広島の被害についても描かれてきましたけども、多くは、その視点は広島の中にある、つまりどれくらいやられたかというお話。でもこれを物語にするときには、その視点は広島の外にあって。思いも寄らないこの原理を使って新型爆弾が作れるかもしれない、と思っていた人たちの話になるなと思って。被害者の視点だけじゃなく、加害者にもなり得たんだと。このテーマは危険かもしれない。でも戦争を多角的に見つめる物語は必要なんじゃないか。勝った負けたではなく、もっと壮大な目線で人間を観察する。自分ではそういうものを見たことないし、見てないからやらなければいけないんじゃないかと思いました」
日記を辿った取材について
「(山口県)岩国に訪ねて行ったことがあって。この日記の中に“石崎くん”という名前が出てくるのですが、戦後解散させられた研究チームですが、石崎さんは岩国の実家に帰って高校の先生をしていたというのが日記の中に少しでてくるんです。岩国で高校の先生をしていたということは「辿れるんじゃないか」と思い、まず知り合いのプロデューサーに相談して、そこから、人づてにたどり辿って、住所までわかった。今までいろんな人を訪ねていったけど、実際に当時の研究室にいらした方は誰一人見つからなかった。みなさんご高齢で亡くなられていたり、連絡が取れなかったり。唯一たどり着けた方だった。広島の調査にも実際に行かれた方なので。手紙を書きました。返事は1ヶ月、2ヶ月待っても来なかった。諦めかけていたら、石崎さんの甥っ子さんからご連絡をいただいた。「叔父は先日亡くなりました。あなたからの手紙が未開封で残っていました。」と。お会いすることはできませんでしたが、先生のメモやノートなどが少しでてきたとのことで、甥っ子さんが「会って話しませんか?」とおっしゃってくれました。石崎さんは戦後、一度は大学の研究を諦め、岩国工業高校で数学の先生になった。復興する日本で生きる若い高校生にたいして「学問は楽しいよ」と熱く語る文集や講演の記録が出てきました。自分は学問を諦めたけども、“それは楽しいもの”と若い人たちに伝えようとする姿が浮かび上がりました。彼はその後大学に呼び戻されて、長く京都大学で研究を続けるわけですが、映画の中で世津が「学校の先生になるんだ」というのはそのエピソードから取っています。
科学者たちの研究してる内容は、僕には難しすぎて、今でもよく分かりません。でも、若い研究者が、何かを見つけようとして集い、研究を続ける熱意は何となく理解できる。夢中になったり、絶望したり、また希望を持って進んだり、の繰り返しで。それは、どこか映画作りに似てるんです。分からないことがある。だからそれを探して映画を作ってみたい、という本能的な「欲」は科学者のそれと重なる。今を生きる自分たちの物語だ、と思いながら撮り進めることができたのはそのためかもしれません」
